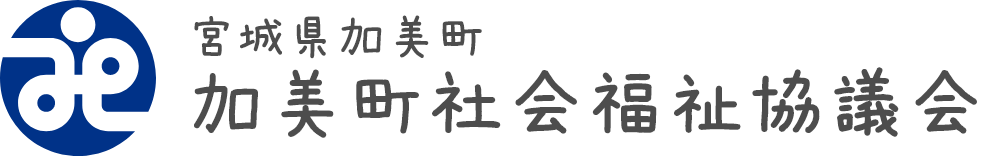生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業とは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう住民の「支え合い・助け合い」を推進する事業です。
加美町社会福祉協議会では、令和4年度から第1層(町全域)の生活支援コーディネーター業務を受託し、町(地域包括支援センター)と連携して各福祉関係者による「協議体」を運営するとともに、以下を行うことによって、その醸成に努めてきました。
- 地域資源及び地域ニーズの把握
- 情報の見える化
- 関係者のネットワーク化・連携
- サービスの開発
- 生活支援の担い手となるボランティア等の養成
- ニーズとサービスのマッチング 等
令和5年度からは、旧3町(中新田地区、小野田地区、宮崎地区)の日常生活圏域ごと(=第2層)にも生活支援コーディネーターを配置し、地域の実情に応じた支援によって推進を図っています。
地域資源および地域ニーズの把握
1.地域資源の把握
地域の中で活動している(住民同士の支え合い活動)等の社会資源を把握します
介護予防
- 高齢者の通いの場
- 集いの場・サロン等
資料:加美町地域資源(お宝)情報 ~地域の集いの場・サロン編~
生活支援
- 買い物支援
- 見守り活動・安否確認
- 除雪
- ゴミ出し支援
- その他
地域ニーズの把握
- 地域の集いの場や老人クラブ活動、地域の自主活動等への訪問を通しての実態把握
- 独居高齢者や高齢者夫婦世帯等の実態把握
- 活動している中で課題と思われていることの把握
地域の問題点の整理
- 地域ニーズと不足するサービス等の整理
情報の見える化(啓発・普及)
地域の現状や新たに把握した活動の紹介などを通して、地域の支え合いの必要性について啓発する
- 広報紙『地域支え合い情報』の発行(年4回)
- 把握した社会資源についてのリスト化(マップ化)
関係者のネットワーク化・連携
- 生活支援体制整備事業協議体の運営(活動報告と話題提供)
- 関係機関とのネットワークづくりを目的とする活動場面根の参加(地域運営組織や既存の団体の話し合いの場面への参加等)
- 町の地域支援事業等への出席
サービスの開発や資源開発に関する活動
- 通いの場(サロンづくり)の立ち上げ支援
- 生活支援サービスの立ち上げ支援
- 地域の課題を整理していく中で必要と思われるサービスの開発
生活支援の担い手となるボランティア等の養成
- 生活支援サポーターの養成
- ボランティア友の会等への支援
ニーズとサービスのマッチング
1.地域支援ニーズとサービス提供団体の活動とのマッチング
- 支援を必要とする方と支援を行う団体や活動を希望する個人ボランティア等との連絡調整